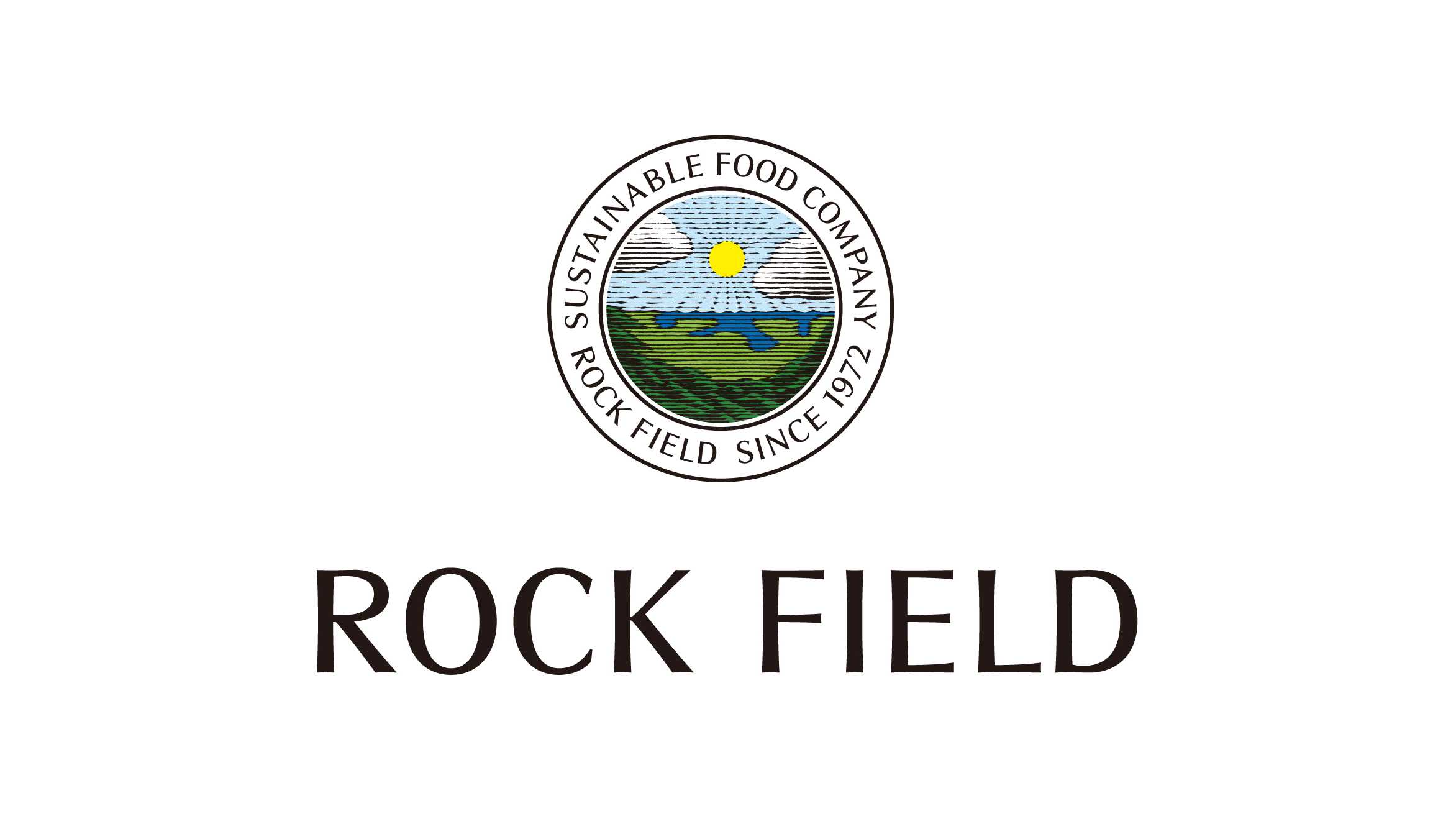ロック・フィールド × カゴメ 『野菜と共に創る未来プロジェクト』
株式会社ロック・フィールド(以下ロック・フィールド)とカゴメ株式会社(以下カゴメ)は2025年3月11日に業務提携契約を締結し、『野菜と共に創る未来プロジェクト』を立ち上げました。両社はバリューチェーン全体に渡る協業を進め、「健康寿命の延伸」「農業振興」「持続可能な地球環境」といった社会的価値と、双方の経済的価値を同時に追求することを通じて、野菜のチカラで彩り豊かで笑顔あふれる食卓を提供するとともに、サステナブルな農業を目指して取り組んでいます。
本日、8月31日(日)は、“野菜の日”として、両社のお客さまや野菜生産者の方をお招きし、野菜を作る人、届ける人、食べる人が一堂に会し、野菜について考えるきっかけとなるイベント「野菜の日 スペシャル トークイベント」を開催しました。野菜を作る人として、野菜生産者の方の思いをお話いただき、野菜を届ける人として、ロック・フィールドとカゴメがものづくりのこだわりをお話しました。イベントの後半では、生産者、ロック・フィールド、カゴメのブースで「野菜を食べる人」であるお客さまとの交流を深め、それぞれの立場から野菜のチカラを見つめ直す一日となりました。
イベント概要
イベント名:
「野菜の日 スペシャルトークイベント」
開催日時: 2025年8月31日(日) 午前の部10:00~12:00 午後の部14:00~16:00
開催場所: ロック・フィールド 東京オフィス1F(東京都中央区日本橋室町4-5-1さくら室町ビル)
参加者 : ロック・フィールドメンバーズ会員 20名、& KAGOME メンバー 20名 計40名
※午前・午後 20名ずつ
イベント内容
1.オープニングセッション (株式会社ロック・フィールド 企画開発本部 本部長 三好 勝寛)
冒頭に、株式会社ロック・フィールド 企画開発本部 本部長 三好 勝寛がご挨拶をしました。
株式会社ロック・フィールド 企画開発本部 本部長 三好 勝寛コメント
「ロック・フィールドとカゴメは野菜のチカラで彩り豊かで笑顔あふれる 食卓を提供するパートナーとして、さまざまな取り組みを進めています。
今日は8月31日の〝野菜の日″ということで、お客さま、生産者の方、カゴメとロック・フィールドが揃い、野菜の今と未来について考えるイベントを企画しました。ぜひこの時間を一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。」
2. 「カゴメトマトジュースプレミアムのこだわり」(カゴメ株式会社 飲料企画部 課長 山口貴之)
カゴメの「農から食卓まで」をつなぐものづくりを象徴する商品として、毎夏に数量限定で販売している国産トマトを100%使用した「カゴメトマトジュースプレミアム」についてお話をしました。
カゴメ株式会社 飲料企画部 課長 山口貴之コメント
「私たちは、畑からお客様までをひとつの流れとして捉え、バリューチェーンを構築しています。
カゴメのものづくりで大切にしているのは“畑は第一の工場”という考え方、そして“畑とお客様のつながり”です。畑で大切に育ったトマトが、“カゴメトマトジュースプレミアム”に姿を変え、お客様の手に届く。一連の流れすべてに責任を持ち、価値へと変えていくことがカゴメの使命であり、他にはない強みです。私たちの商品は、生産者の想い、技術者の知恵、そしてお客様の笑顔がつながって、初めて完成する一杯です。」
3. 「野菜の日特別メニューのこだわり」(株式会社ロック・フィールド 企画開発本部 明山計子・林若菜)
ロック・フィールドの各ブランドで展開している「野菜の日」販促について、目玉商品である「野菜一日分350(サンゴーマル)サラダ」の紹介を中心にお話しました。
株式会社ロック・フィールド 企画開発本部 林若菜コメント
「ロック・フィールドでは、8月31日を〝野菜の日″として大切に考えてきました。今年は『野菜のチカラで、未来を耕そう』をテーマにし、特別商品の販売を行っています。
野菜一日分350(サンゴーマル)サラダは、摂取不足が課題となっている『野菜量1 日 350g』を1パックで手軽に摂れるサラダです。ドレッシングにカゴメの 野菜飲料 『野菜一日これ一本』を、トマトはカゴメの 生鮮野菜『高リコピントマト』 を使用しています。」
株式会社ロック・フィールド 企画開発本部 明山計子コメント
「野菜には、おいしさだけでなく、食感や香り、彩り、栄養などたくさんのチカラがあります。そのチカラを活かして皆さんにお届けできるよう、もっと楽しく、おいしく野菜を食べていただける工夫を考え、サラダを通して生産者様とお客様をつなぎ、健康で幸せな暮らしを提供できるように努めていきます。」
4. 「育てる人の声を聞く ~種と土と共にある野菜の物語~」(北野農園 代表 北野忠清様、農業生産法人 有限会社四位農園 取締役 耕種部長 東永光俊様)
ロック・フィールドのサラダに使用している「泉州水ナス」を栽培されている北野農園代表の北野忠清様、ごぼうを栽培されている農業生産法人 有限会社四位農園 東永様より、野菜の生産についての知識や、生産者の思いをお話いただきました。
北野農園 代表 北野忠清様コメント
「北野農園は、先祖代々、大阪府貝塚市で泉州水なすと、その原種である貝塚澤なすの栽培をしています。水なすの歴史は古く、400年前の教科書にも記載があります。風土・治水・水にまつわる信仰の3つの要素が揃って、これまでつながれてきました。ぬか漬けだけでなく、サラダという今の時代の食べ方で全国の皆さんに味わっていただける事に大きなエネルギーを感じています。今後も水なすを地域として大切につないでいきます。」
農業生産法人 有限会社四位農園 取締役 耕種部長 東永光俊様コメント
「四位農園は、宮崎県で60年前からごぼうやほうれんそう等の野菜やお茶を栽培しています。火山灰によって3mほどの黒土が積もっており、長いごぼうを作ることができます。その土の微生物を元気にするため、たい肥作りにこだわって栽培しています。ロック・フィールドには、ごぼうの風味を保つために土付きのままごぼうをお届けしています。サラダを食べる際には、ぜひ風味を感じていただきたいです。」
5. ブース展示、自由交流
会場には、ロック・フィールド、カゴメ、北野農園、四位農園のブースが設けられ、各ブースでお客さまとの交流が行われました。
ロック・フィールドのブースでは、サラダの開発ストーリーについて開発担当者がお話し、お客さまから感想やご意見をいただきました。
カゴメのブースでは、「カゴメトマトジュースPREMIUM」の紹介のほか、推定野菜摂取量を測定できる「ベジチェック®」をお試しいただきました。
北野農園のブースでは、水なすを展示して実際に触っていただいたほか、水なすにまつわる書物も展示し、歴史についてもお話をしました。
四位農園のブースでは、土付きのごぼうを展示し、ごぼうの長さ、太さを触って体感していただき、黒土の特徴も知っていただきました。
ご参考~これまでのプレスリリース~
2025年3月11日 業務提携契約の締結について
https://www.rockfield.co.jp/news/detail.html?relyear=2025&id=20250311-a39f8b9d
2025年8月6日 「ロック・フィールド 野菜の日2025」全ブランドで販促を実施
業務提携後初!カゴメ㈱との協業プロジェクト商品が期間限定で登場
https://www.rockfield.co.jp/news/detail.html?relyear=2025&id=20250806-e5288b3b
【株式会社ロック・フィールド】
1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国のデパ地下や駅ビルに「RF1」など6つのショップブランドを302店舗(2025年8月末現在)および冷凍食品ブランド「RFFF(ルフフフ)」を展開。
「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」の価値観のもと、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
【カゴメ株式会社】
1899年創業。長期ビジョン「トマトの会社から野菜の会社に」を掲げ、トマトケチャップや野菜飲料、調理食品、生鮮野菜、冷凍野菜など、野菜の価値を活かした商品や健康サポート事業を展開。海外では、北米・欧州・豪州・アジアの事業会社が連携し、フードサービス業態や食品製造業向けにトマト加工品を製造・販売。また、環境変化に適応した品種の研究や栽培技術の開発に取り組んでいます。