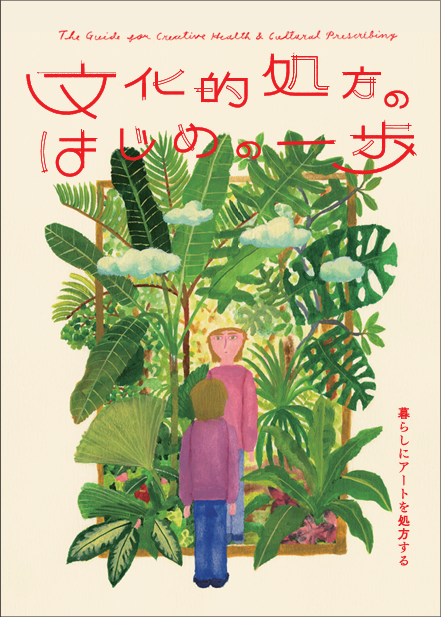国立アートリサーチセンター(略称:NCAR、センター長:片岡真実)は、東京藝術大学が拠点となり、大学、美術館、医療・福祉の組織や自治体など42の産官学と連携する「共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点(略称:ART共創拠点)」に参加し、健康の社会的格差を縮める「文化的処方」を推進しています。
その一環として「文化的処方」の実践をサポートするためのガイドブック「
文化的処方のはじめの一歩」を制作しました。ウェブマガジン「ああともTODAY」にて2025年3月17日より公開します。
本ガイドブックは、アートやケアに関心のある個人の方や市民団体、美術関係者や医療・福祉関係者などに向け、「文化的処方」の定義や、日本の美術館・病院・市民団体・大学・個人店での5つの事例を、誰もが分かりやすく参考にできる形で紹介します。
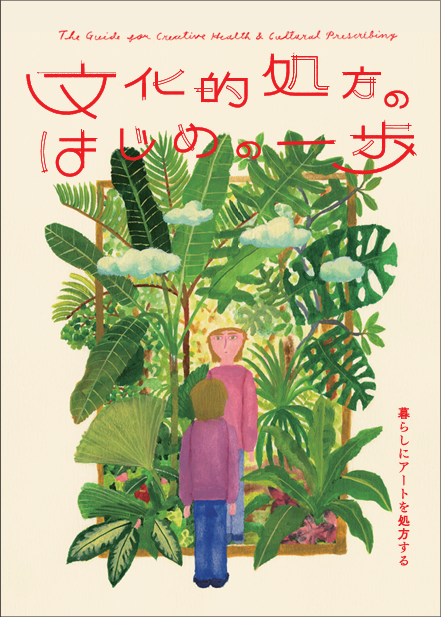
 (左)「文化的処方のはじめの一歩」表紙
(左)「文化的処方のはじめの一歩」表紙
(右)文化的処方の事例紹介
「文化的処方のはじめの一歩」概要
内容:「文化的処方」の定義・意義
日本の美術館・病院・市民団体・大学・個人店での事例紹介
仕様:B5変型/36ページ/中綴じ
対象:アートやケアに関わる個人の方や地域でのつながりに関心のある市民団体、
美術関係者や医療・福祉関係者
閲覧方法:ウェブマガジン「ああともTODAY」にて2025年3月17日(月)より公開
サイトURL:
https://aatomo.jp/guidebook
◆「文化的処方」とは
「文化的処方」とは、健康や幸福によい影響を与えるアートや文化活動、そしてそれらを活かした社会的な取り組みのことです。たとえば、アートや文化活動を体験することでストレスが軽減したり、食欲が増して健康を保つ助けになったりすることが、近年の研究で明らかになっています。こうした取り組みは、超高齢社会で課題となっている認知症などの慢性疾患や孤独といった、医療や福祉の重要な課題に役立つとされ、欧米をはじめとする多くの地域で実践が進められています。本活動では、イギリスで進む「つながりをつくる処方/ Social Prescribing」や「クリエイティブ・ヘルス / Creative Health」を参考にしつつ、日本の医療や福祉システムと連携し、地域の文化的環境を活かした活動を進めることで、社会課題の解決を目指しています。
◆「ああとも」プロジェクトとは
「ああとも」は、美術館や博物館など文化的拠点が持つリソースを活用し、「文化的処方」を社会に広げていくことを目的として「ART共創拠点」内のプロジェクトとして2023年に始動しました。NCARラーニンググループの稲庭彩和子主任研究員と東京藝術大学の映像研究科長桐山孝司教授の合同チームが企画運営を行い、様々な地域の自治体、医療や福祉の団体、アートコミュニケータ等が連携しプロジェクトを進めています。
◆国立アートリサーチセンター(NCAR)の事業について (
https://ncar.artmuseums.go.jp/)
NCARは「アートをつなげる、深める、拡げる」をミッションに、情報収集と国内外への発信、コレクションの活用促進、人的ネットワークの構築、ラーニングの拡充、アーティストの支援など、わが国の美術館活動全体の充実に寄与する活動に引き続き取り組んでいきます。
JST「共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点」について
東京藝術大学を中核として、アート、福祉・医療、テクノロジー等の専門機関や企業、自治体を含む42組織が、社会課題解決のための知識や技術を持ち寄り、「文化的処方」を開発し、地域社会に実装することで、誰もが生涯を通じて社会参加でき、幸福で健康的な生活を送り続けることのできる社会の共創を目指しています。 (
https://kyoso.geidai.ac.jp/)